食品ロス削減
基本方針
当社は創業以来、「食材すべてを無駄にしない」という指針が根付いており、1970年代から吉野家で牛丼をつくる際に発生する牛脂リサイクルを行っています。その後、この指針に加えて、「食」に携わる企業として、食品廃棄物の最終処分量を減らしていく取り組みは社会的な責務であると捉えており、マテリアリティのKPIのひとつに食品ロス削減を掲げてグループ全体で地球環境に及ぼす影響を軽減するさまざまな取り組みを追求し続けています。

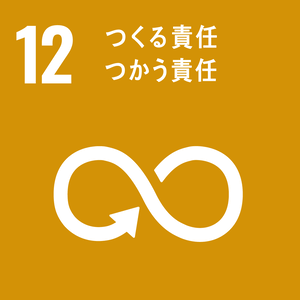

| リスク | 機会 |
|---|---|
|
|
KPI
| KPIの設定 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2027年度目標 | 2029年度目標 |
|---|---|---|---|---|
| 国内工場から排出する廃棄物の再生利用※ | 53% | 62% | 55% | 56% |
吉野家、はなまるの国内8工場の再利用率です。
活動事例
国内7工場
- 工場で発生する食品残渣のリサイクル率は2023年度以降、100%です。
| 2020年度 | 90.3% |
|---|---|
| 2021年度 | 92.2% |
| 2022年度 | 99.9% |
| 2023年度 | 100.0% |
| 2024年度 | 100.0% |
吉野家の取り組み
東京工場
- 食肉加工センターで発生する切り落としの肉をハンバーグ原料用に他社へ販売しています。
- 野菜加工センターで発生する規格外端材は吉野家のソースや「かるびのとりこ」でスンドゥブのスープのだしに使用しています。
- 2023年から、東京工場で規格外となっていた玉ねぎ端材を乾燥処理し、食用パウダーとして利用するアップサイクルの取り組みを行っています。また、2024年2月以降は東京工場にASTRA FOOD PLAN株式会社が開発した過熱蒸煎機を導入し、瞬時に殺菌・乾燥・粉末化し、食材の風味と栄養価を残した食品素材原料として有効活用を行っています。外食企業のフードロス対策として高評価を得ています。
【牛丼に使用する食材すべてを無駄にしないために 玉ねぎの規格外端材をアップサイクル】
京都工場
- 加工時に発生する玉ねぎやキャベツなど野菜の残渣を自社の畑で発酵させて良質なたい肥土壌をつくり、その土壌で育てられた野菜を加工、商品化する循環型アップサイクルに取り組んでいます。



吉野家店舗
- 吉野家では、店舗におけるお客様の食べ残しを顧客満足の指標として捉え、発生抑制に取り組んでいます。全店で食べ残しを定性的かつ定量的に記録・分析し、異常値が出た際の本部における対応として、味のブレと関連付け、厨房オペレーションを修正することで味の均質化を図り、結果的に食べ残しを出さないことにつなげています。発生した食品残渣(食べ残しおよび厨房調理くず)については、店舗ごとに飼料化・肥料化などによる食品リサイクルを実施しています。
- お客さまのご来店数を予測したデータと、牛肉を煮込むタイミングを連動させることで、適切な調理と食材管理を行なっています。注文を受けてから店内で調理をするシステムは、できたてを提供できることに加え、ロスが発生しないというメリットと品質向上の両方につながっています。
- 牛丼の調理過程で発生する牛脂は1976年から油脂化・油脂製品化による100%リサイクルを全店(離島を除く)で実施しています。各店舗から回収した牛脂は、当社物流センターに収集した後、飼料や脂肪酸、製品原料、発電燃料として、油脂会社から飼料・化学工場、メーカーへ売却されます。
食品残渣の再生利用実施率(吉野家全体)
| 2020年度 | 74.0% |
|---|---|
| 2021年度 | 74.4% |
| 2022年度 | 83.7% |
| 2023年度 | 83.8% |
| 2024年度 | 77.4% |
牛脂油缶出荷数(吉野家店舗全体)
| 2020年度 | 5,751t 383,400本 |
|---|---|
| 2021年度 | 5,591t 372,706本 |
| 2022年度 | 4,239t 282,615本 |
| 2023年度 | 3,767t 251,167本 |
| 2024年度 | 4,757t 317,133本 |
はなまるうどんの取り組み
香川工場、千葉工場、静岡工場、沖縄工場、北海道工場
- うどんを最先端の冷凍技術を用いて賞味期限を延長しています。このうどんは冷凍自販機で販売するほか、子ども食堂へ提供しています。
- 2022年からは高松工場の廃棄うどんの4割を高松市へ提供し、集めたうどんから発生するガスを使って発電させるバイオマス発電の実験に協力しています。
- 千葉工場、静岡工場、沖縄工場、北海道工場の廃棄うどんは、リサイクル会社を通して、生うどんに含まれる塩分を取り除き、飼料向けの原材料として販売する取り組みを行なっています。
- うどん端材をお酒へとアップサイクルする研究を行っています。
はなまるうどん店舗
はなまるの店舗では食品リサイクル率50%を目指し、お客さまのご来店数を予測したデータと麺をゆで上げるタイミングを連動させることで、適切な調理と食材管理を行なっています。また、廃棄を低減する取り組みとして、製麺工程でホールディングタイムの延伸を図り、ゆで上げ後のおいしさを長く維持できるうどんの開発を進めています。
フードロス率(千葉工場、静岡工場、沖縄工場、北海道工場)
| 2020年度 | 7.5% |
|---|---|
| 2021年度 | 8.4% |
| 2022年度 | 0.0% |
| 2023年度 | 0.0% |
| 2024年度 | 0.0% |
食品残渣の再生利用実施率(はなまるうどん全体)
| 2020年度 | 44.2% |
|---|---|
| 2021年度 | 40.3% |
| 2022年度 | 33.2% |
| 2023年度 | 33.0% |
| 2024年度 | 32.7% |
高松工場からの高松市への廃棄うどん提供量
| 2022年度 | 2.5t |
|---|---|
| 2023年度 | 6.9t |
| 2024年度 | 7.0t |
宝産業
10年以上前から、調味料だけでは出せない肉の旨味がたっぷり詰まっているチャーシューを煮たタレを再利用し、つけ麺のタレや煮卵のタレとして販売しています。また、チャーシューを成形する際に出た端材は、他の肉と混ぜ合わせて加工し、餃子や焼売、醤(ジャン)、肉味噌、さらにはスープを炊く際の原料などにも使用しています。この循環作業が功を奏し、近年肉の端材破棄は出ていません。廃棄麺についても飼料・肥料・燃料などリサイクルを行っています。
受賞歴
東京工場で2023年以降、実施する「食材加工時に廃棄される規格外の玉ねぎ端材のアップサイクル、ならびに持続可能なスキーム構築」に対して、環境省及び消費者庁が実施している「令和6年度食品ロス削減推進表彰」で「環境事務次官賞」を受賞しました。